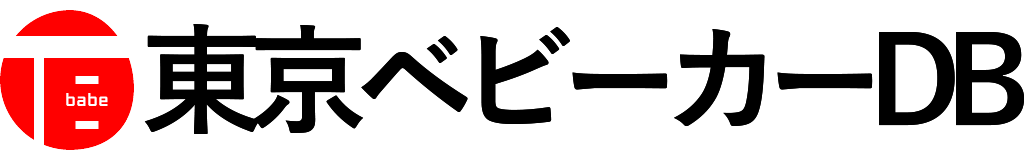【2025】Amazonブラックフライデーで買うべきベビーカーとベビー用品の目玉商品

国内メーカー派の人にはこちらが正解早いものであと一ヶ月もすればクリスマスです。散財シーズン真っ只中ですね。そんな中、ここぞ!とばかりにAmazonでも遂に年に一度のセールイベントがやってきてしましました。それが、Amazonブラックフライデーです。>Amazon.co.jp:ブラックフライデーセールベビーカー特選タイムセール–すべての割引\もうすぐ終了。ベビーカー小物に注目/ブラックフライデーでおすすめのベビーカー日用品の目玉商品今が最安値のAmazonデバイス開催期間は2024年11月29日(金)0:00〜12月6日(金)23:59までの約1週間です。ブラックフライデーブラックフライデーとは、アメリカの祝日「感謝祭(11月第4木曜日)」の翌日金
曜日のこと。アメリカ最大規模のセール「クリスマスセール(ホリデーシーズン)」の初日にあたる日で、国内の小売販売店が便乗して一斉にこの時期にセールを行います。つまり、『年に一度の(便乗)ビッグセール』という意味合いが強いです。管理人パパセールの目玉商品としては、なんといってもAmazonデバイスやガジェット・家電などAmazonで良く売れている商品ですが、我らがベビーカーもしっかり安く(50%OFF以上の商品も)なります。楽天市場のセールイベントとの違いは?11月は「楽天お買い物マラソン」「楽天ブラックフライデー」と楽天市場のセールが続いていました。一年のうちでも楽天のセールが多いのがこの時期(逆に10月はほとんど無かったのですが)。それで、「楽天市場のセール商品も見てきたけれど、欲しい商品がそこまで安くないわよ!」「ポイント還元!還元って、私が欲しいのは直接値引きよ!」「買い回りとかややこしいルールを強制するんじゃないわよ!」とか、憤慨されていた人も多いのではないでしょうか(笑)私はポイント付与による消費者の囲い込みって実はあんまり好きではありませんが、そこが最安値で買える場所で、ショップ評価さえ確かなら甘んじてそれを受け入れよう・・・な主義です。しかし、「ややこしいわ!」と楽天を苦手とする人も多いことでしょう。とくに、男性に多いかな。。そんな楽天を描写する一方で、「ではAmazonとの違いは?」に一言でお答えします。それは、ベビーカーの販売価格そのものが安くなるです。楽天みたいに「ポイント還元●%!」だとか「エントリーで!」とか言いません。掛け値なしに直球で安いということです。あれっ?サイバーマンデーは?Amazonが毎年、12月の第2月曜日に開催しているのが『サイバーマンデー』です。ブラックフライデー同様、各種商品が安くなります。一昨年(2022年)は、ブラックフライデー&サイバーマンデーとして5日間の開催でしたが、昨年に引き続き2024年もブラックフライデーが従来よりも長い期間(1週間)となったこともあって、サイバーマンデーの実施が無いみたいです。つまり、Amazonは『ブラックフライデー&サイバーマンデー』を統合してAmazonブラックフライデーに変えたということ。ということで、今回のブラックフライデーこそが『今年最後のビッグセール』と考えて良いでしょう。では、どのベビーカーが安くなる?去年も、一昨年も記事を綴ってきましたが、その内容が下記のページにあります。投稿が見つかりません。時間のない人のために、ページの概要を一言で話すと、2022年に開催されたAmazonブラックフライデーでは、国内メーカー商品の一部が大きく値を下げて登場しました。ブラックフライデー対象ブラックフライデー対象外アップリカサイベックスコンビバガブーピジョンイングリッシーナリッチェルdoonaRISUそういえば、通常4万円以上もする商品がこんな価格でも出品されていましたね。管理人パパ投げ売りにも程がある・・・出品事故なのか、、ということで、今年の目玉出品もコンビ、アップリカ、ピジョン、リッチェル、エアバギー、日本育児、カトージなどの国内メーカー商品が中心になると予想します。また、海外ブランドに目を向けてみると、私の日頃の値動き観察からの勘では、下記のブランドの中から目玉商品が登場するのではないかと見ています。Joie、グレコ、JisforJeep、サイベックス&CBX(サイベックスのセカンドブランド)あたりでしょうか。時間になったらこちらから↓(2024年11月29日0:00~)>Amazonブラックフライデーのセール対象ベビーカー管理人パパいまあなたにできることは、今の価格を写メっておくことですAmazon側の操作でセール直前に価格を定価に戻す(見せかけの値下がり幅を作るための値上げ)のを見破るためRISUごめん、隊長は40代なので、今の子は写メって言っても通用しないよね。スクリーンショットのことです【予習】Amazonで売れ筋のベビーカー・ランキングセールがはじまるとそれにつられてランキングが大きく変動して(濁って)しまうため、予習も兼ねて今のうちに値付けが変わる前のランキング順位をチェックして置くと良いです。>Amazon.co.jp:ブラックフライデーセールベビーカー特選タイムセール–すべての割引管理人パパJoieの商品が1位になるなんて以前なら考えられませんでした。ここ2年で浸透したブランドですね。トイザらスユーザーに支持層が多い印象。>売れ筋ランキング:両対面ベビーカーの中で最も人気のある商品RISUリベルにgbポキットが肉薄していますが、実際の走行性能は大きくリベルですね。ただし、リベルも小さいですがポキットはさらに小さくなるのが捨てきれない!>売れ筋ランキング:背面ベビーカー・バギーの中で最も人気のある商品管理人パパここでもJoieが人気。お出かけ帰りの買い物にはカゴの大きいグレコのシティトレックが人気。>売れ筋ランキング:3輪ベビーカーの中で最も人気のある商品RISUJoie、カトージとカトージ取り扱い商品が続いてますね!>売れ筋ランキング:二人・多人数用ベビーカーの中で最も人気のある商品【随時追加】で、目玉商品はどれなの?11月29日0:00過ぎに目ぼしい商品を見つけ次第、下記のようにこちらにリストしていきます。 [ザノースフェイス]ベビーシェルブランケット THENORTHFACE(ザノースフェイス) ¥10,111 15%OFFクーポン配布中! ベビーカー用フットマフ・シェルブランケットの人気ランキング2024-2025 カトージベビーカー2-Seaternextグレー41447 カトージ ¥31,400 今年一番安い Joieベビーカーライトトラックス3DLX3輪ベビーカー1か月~(ブラック) Joie(ジョイー) ¥31,800 地味だけど近所と公園用なら◎ Aprica(アップリカ)A型ベビーカースムーヴプレシャスAB1か月~36か月まで3輪タイプ(ベージュ)2184599 Aprica(アップリカ) ¥65,000 たぶん今年一番安い 【発売開始記念プレゼント付!】サイベックスメリオカーボン2025 ¥74,690 ポイント還元率なら楽天の方がお得 【数量限定バンパーバープレゼント】サイベックスリベル2025年 ¥29,700